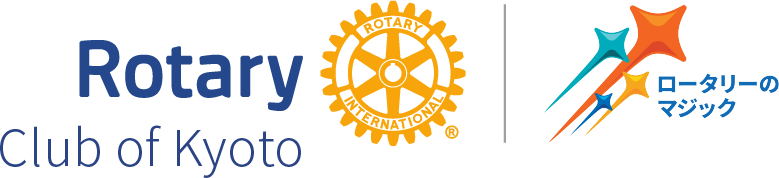|
2022.2.2
― 新会員スピーチ ―
「建築道具の歴史と環境に配慮したものづくり」
名越 健二 君
日本建築をつくった道具の歴史の旅へ
日本の大工道具は、世界でも稀にみる多様性と独自性を誇ります。ルーツの多くは中国にありますが、日本の大工道具の変遷を顧みると中国の道具を全面的に受容せず、名もなき職人が知恵と工夫を積み重ね多様な用途・目的に応じた様々な道具が誕生し、時代の建築を彩ってきました。
例えば、飛鳥時代建立の法隆寺は大ぶりで力強く、江戸時代建立の桂離宮は繊細で装飾豊かであるなど、千年の間に変化を遂げた道具が作り出した造形美は今も見るものを魅了してやみません。
ただ残念なことに、大工道具そのものは、実用を目的としているが故に、数百年も前の道具が大事に保存されていることは滅多にありません。しかし発掘や、建築部材に残った歯形などの痕跡、絵巻等に描かれた断片情報を繋ぎ合わせることが出来た時ダイナミックな軌跡が浮かびあがりロマンあふれる歴史の旅に我々を誘ってくれます。
環境に配慮したこれからのものづくりについて
世界中で脱炭素社会の実現、カーボンニュートラルが叫ばれている中、建築の世界では木造建築が見直されています。その用途は住宅のみならず高層の一般建築物にも採用されはじめています。木造建築がなぜカーボンニュートラルに寄与するのか。それは二酸化炭素をたっぷり吸収した木材を伐採することで木の中に封じ込め、建材として利用することで固定化することができるためです。
当初は法規制が緩やかな海外で先行していましたが、日本でも2000年の建築基準法改正により、一定性能を満たせば木造建築が可能となり、それが鉄やコンクリートと同じ性能を持った燃えない木造建築、耐火木造建築と呼ばれ、高層化を目指した開発がスピード感を持って進められています。今回、最先端の構工法をご紹介しながら、日本の木造建築が目指すカーボンニュートラルの世界の一端をご理解いただければ幸いです。
京都ロータリークラブ
〒604-0924 京都市中京区河原町通御池上るヤサカ河原町ビル4F
Tel 075-231-8738 Fax 075-211-1172
office@kyotorotary.com
|