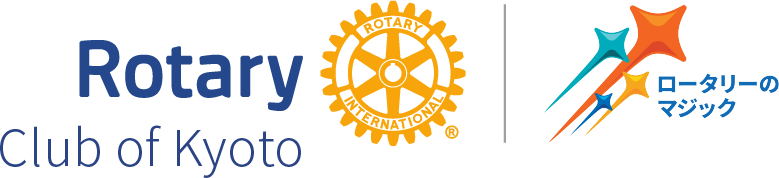|
2012.6.13
「『方丈記』八〇〇年の時に」
下鴨神社 禰宜
嵯峨井 建 氏
「ゆく河の流れは絶えずして、しかももとの水にあらず。よどみに浮かぶうたかたは、かつ消えかつ結びて、久しくとゞまりたるためしなし」。日本三大随筆の一つとされる『方丈記』の書き出しである。今年は「古典の日(11月1日)」のテーマ作品として『方丈記』が取りあげられ、関連する記念行事が予定されている。
『方丈記』の作者、鴨長明は下鴨神社の神主家の出身。父は糺ノ森にある河合神社の禰宜で、その後継者と目されていた。ところが、仲間うちに足を引っ張られて、禰宜になることができずに、出家した。もともと感性豊かで、琵琶の名手であり、第一級の歌人でもあった。
出家した長明は、まず大原に行き、その後は日野の山中(現在の伏見区)に隠れ住みながら『方丈記』を執筆した。平安の終わりから鎌倉時代にかけた、動乱の世であった。大火、大風、飢饉、大地震などの災害と、逃げまどう人々の姿をリアルに描いた。国文学者の浅見和彦氏は、「災害文学」と呼べると指摘する。
災害のあった現地に出掛けて死体の数まで勘定していることから、「ルポライター長明」といってもよい感じがする。元暦(げんりゃく)元年に京都を襲った大地震の描写は、3.11の凄まじい映像と二重写しになる。
京都産業大学の小林和彦氏は『方丈記』について、長明が自分のことを生々しく書いた「日本最初の私小説」だとおっしゃる。確かにこの作品には、そういう一面もある。
長明が住んでいた方丈の庵についても『方丈記』の中に詳しく描写されている。5.5畳くらいの広さ。高さは約2メートル。阿弥陀の絵像や普賢菩薩の絵を飾り、『往生要集』と琴、琵琶などをかたわらに置いていたという。
この庵は中村昌生先生の設計で復元され、現在は河合神社に据えてある。機会があればご覧いただきたい。
長明は50歳で出家し、60歳余りで亡くなった。『方丈記』は彼の最後の著作で、遺書であり遺言だと思う。自らをしみじみと顧み、今の時代を考えるきっかけとして、3.11以後の日本人が、深くよむべき古典であると思う。
京都ロータリークラブ
〒604-0924 京都市中京区河原町通御池上るヤサカ河原町ビル4F
Tel 075-231-8738 Fax 075-211-1172
office@kyotorotary.com
|