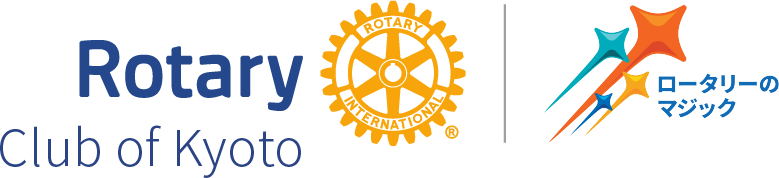|
2015.1.14
「京舞について」
京舞 井上流五世家元
井上 八千代 氏
「京舞 井上流」の初世家元は、井上サト(明和4・1767年生)です。ご縁があって15歳で近衛家に奉公に上がり、そこで舞を習って、指南役を務めるまでになりました。宿下がりの時、井菱の紋と共に「玉椿の八千代までそなたを忘れぬ」というお言葉を頂戴し、それに因んで「八千代」と名乗り、舞の井上流を創始しました。初世の姪・アヤが二世を継ぎ、祇園に引っ越したことから、祇園とのつながりが深まっていったようです。
初世、二世の時代に、私どもが得意とする、能楽に題材を得た地唄の曲が作られました。井上流の財産として今に受け継がれています。三世(春子)は能楽シテ方観世流・六世片山九郎右衛門と結婚し、片山春子と名乗った時期がありました。
明治5年の第1回京都博覧会の折に、京都に来るお客様へのおもてなしとして、祇園の芸妓による総踊りを舞台で披露する話がもちあがりました。祇園・万亭(現在の一力亭)の当主、杉浦治郎右衛門から三世に声がかかり、共に考えた舞台が「都をどり」の起源になりました。
三世八千代は体も大きく、作る作品もダイナミックでした。四世八千代は男勝りの性格でしたが、実は娘方を繊細に舞う姿が四世の代表的な舞だったと私は思います。70歳代の四世による「艶もの」の舞、それが私を舞の道に導いてくれました。90歳代になると、私に八千代の名前を譲り、井上愛子という名に戻りました。その頃の舞には、全てのことから解き放たれた、あるがままの姿と、老いの力強さを見ることができました。
舞と踊りは異なります。舞はもともと「回る」ことです。踵を上げて摺り足で進みます。踊りは「跳躍」から発しているので躍動的です。ドラマ性もあります。舞は、静の中に心象風景を表わすので、辛気臭いと思うかもしれませんが、繰り返しご覧いただくことによって味わいが増すだろうと思います。
舞であることを忘れずに「京舞 井上流」を守ってまいります。お客様の目が素晴らしい舞い手を育てます。今後も変わらぬ応援をお願い致します。
京都ロータリークラブ
〒604-0924 京都市中京区河原町通御池上るヤサカ河原町ビル4F
Tel 075-231-8738 Fax 075-211-1172
office@kyotorotary.com
|