
保護司は、犯罪や非行をした人の更生を図り、社会に復帰した彼らが地域の一員として生活できるようにしていくための活動をする。これを「更生保護思想」という。
近代的な更生保護思想の源流は、1888(明治21)年、静岡監獄の副監獄長だった川村矯一郎さんと、実業家の金原明善さんが設立した「保護会」にあるといわれている。
川村さんが静岡監獄で指導した吾作さん(仮名)が出所後、周囲の理解を得られず、住居や仕事を得る術もないまま、自ら命を絶った。現実の厳しさを改めて痛感した川村さんは金原さんと共に、「静岡県出獄人保護会」を設立した。
同会の設立趣意書は、現在の更生保護の基本である「更生保護法」第1条に継承されている。
「犯罪や非行をした人に対して適切な処遇をする」「再び犯罪をすることを防ぎ、非行をなくしていく」「地域社会の安心安全を維持していく」といった内容だ。民間の力で切り開いた活動が、更生保護思想の源流となったことがわかる。
保護司とは、犯罪や非行をした人(保護観察対象者)の立ち直りを支える、地域の民間ボランティアだ。保護司法に基づいて、法務大臣から委嘱された非常勤の国家公務員。ただし、給与は支給されない。保護司は、民間人としての柔軟性、地域の実情に通じているという特性を生かしながら、犯罪や非行をした人の保護観察にあたる。社会に復帰してきた時に、安全安心な社会の一員として生活できるように、居住や就業先などの環境調整や相談といった活動をする。
保護司の要件は、保護司法に定められている。社会的信望を有すること。熱意と時間的な余裕を有すること。生活が安定していること。健康で活動力を有すること。これら四つがある。
保護司の全国の定数は52,500人で、現数が46,043人。充足率は87.7%だ。平均年齢65.4歳。職業は会社員のほか宗教家も多い。京都府内には22の保護司会があり、保護司はそれぞれ地区の保護司会に所属して活動している。
クラブ・フォーラムでは、保護司の活動事例を紹介する。保護司について理解を深めていただく一助になればと願っている。
スピーカープロフィール
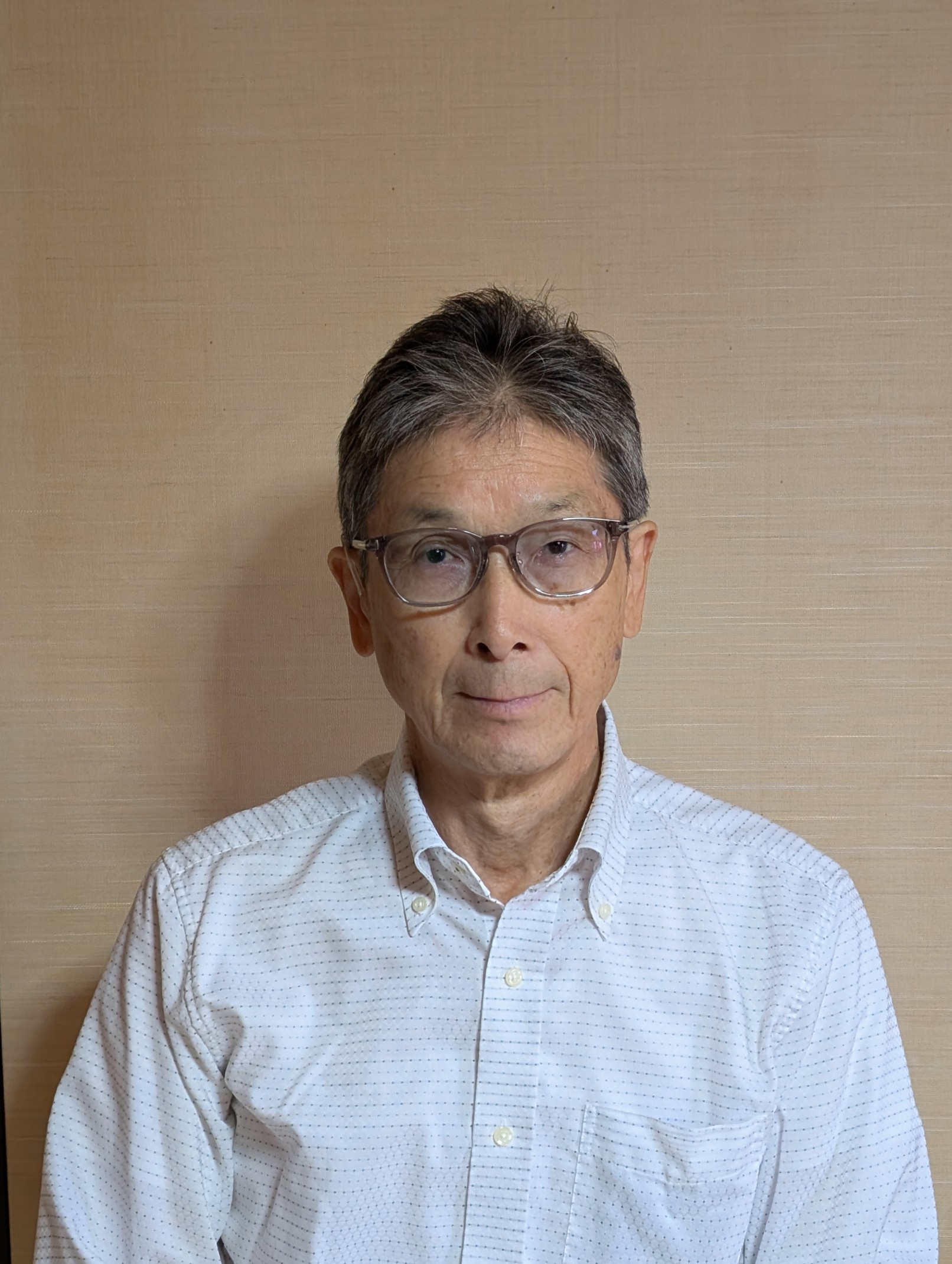
池坊短期大学 教学事務部長 梶村 健二(かじむら けんじ)氏
国際基督教大学教養学部、同志社大学法学部を卒業され、京都市教育委員会で指導部担当部長、中央図書館長、総合教育センター長等を歴任され、退職後2007年に嵯峨美大教授に就任。同時期に保護司の活動を開始されました。その後、京都市教育委員会教育委員、東山保護司会会長を経て、現職をお務めです。
昨年4月に大津市で保護司が保護観察対象者から殺傷されるという大変痛ましい事件があり、保護司の役割や職務などが大きく話題になりました。

